海外転勤や海外移住した場合、日本の証券会社で保有する株式等はどうなるのでしょうか?
グローバル化に伴い海外転勤が想定される会社にお勤めの方も増えているでしょう。また、私のように将来海外に住んでみたいと考えている人もいるかもしれません。
一方で、日本の証券会社や銀行は日本に住んでいない「非居住者」に対して非常に冷たい態度を取るのも事実です。
本記事では主要ネット証券各社の海外転勤時の取り扱いをまとめました。海外転勤の可能性が高い方は、楽天証券へ口座開設しておくことをお勧めします。
(本記事は2023年1月14日時点の情報を基にアップデートしました。)
海外転勤が決まると保有する株式等はどうなるのか?

主要ネット証券であるSBI証券、楽天証券、マネックス証券の非居住者の取り扱いについて確認していきたいと思います。
各社の取り扱いを簡単に整理すると以下の通りです。
- 非居住者になると基本的な取引はできない
- 3社とも取引は制限されるものの金融商品は保有し続けることができる
- 3社とも外国株式の保有はできない
- 楽天証券は特定口座/NISA口座の維持が可能
日本の「非居住者」になると、日本の証券会社では基本的に株の売買ができません。
ただし、一時的に「非居住者」になるのであれば、帰国するまで株式等をそのまま保有することが可能です。
以下では、各証券会社の対応について詳細に確認していきたいと思います。
SBI証券
SBI証券では海外転勤時も口座を保持して投資商品を保有し続けることが可能です。ただし、日本株式と日本国債限定です。
当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国し、「(本邦)非居住者」に該当される場合、原則として日本株式および日本国債以外の金融商品等をお預かりすることはできません。
また、非居住者になると特定口座での管理はできず、一般口座の管理になってしまいます。帰国した際に「特定口座」へ戻すことができるかどうかは記載されていません。
帰国後に「特定口座」に戻してもらえるかどうかは非常に重要です。なぜなら、仮に一般口座のままであれば、帰国してからは税金の計算などを全て自分で行う必要が出てくるからです。
SBI証券を利用されている方は、帰国した際に「特定口座に戻してもらえるか」を出国前に確認すべきです。
楽天証券
楽天証券ではSBI証券よりも具体的に口座維持の条件が記載されています。
楽天証券では出国期間に基づいて口座を維持できるかどうかが決まります。特に、5年以上あるいは期間未定の方は口座の維持ができません。
| 出国予定期間 | 手続き |
|---|---|
| 1年未満 | 手続きは不要 |
| 1年以上〜5年未満 | 事前手続きで維持可能 |
| 5年以上 | 口座維持不可 |
| 期間未定 | 口座維持不可 |
注:渡航先が米国の場合は1年未満でも事前の手続きが必要な場合あります。
出典:楽天証券HP
また、楽天証券では出国期間が1年以上〜5年未満であれば、帰国された際に特定口座へ戻すことが可能と明記されています。また、海外転勤であればNISA口座の維持も可能です。
しかし、SBI証券同様に以下の条件があります。
保有できる商品:国内株式(ETF・REIT等を除く)、および個人向け国債
出典:楽天証券HP
出国期間中は国内株式か個人向け国債しか保有することができません。ETFやREITもダメです。
高校中退投資家のように米国株をメインで保有されている方にとっては厳しいルールです。
マネックス証券
マネックス証券では、所定の手続きをすれば休眠口座として口座を維持できるものの、楽天証券と同様に外国商品は出国前に売却する必要があります。
- 外国商品や信用建玉などを保有されている場合は、出国前に売却・決済していただくようお願いいたします。
- 特定口座や非課税口座(NISA)は国内居住者が利用できる制度のため、廃止させていただきます。
出典:マネックス証券HP
また、マネックス証券では楽天証券と違ってNISA口座が維持できないことが明記されています。
租税特別措置法では一定の条件を満たす場合にNISA口座の継続適用が可能ですが、当社ではその適用は行っていないため、非居住者となる場合には、NISA口座の解約が必要となります。
出典:マネックス証券HP
海外転勤時にどうすればよいのか?
楽天証券で日本株を保有するのが最適解!
結論として海外転勤などの可能性がある人は楽天証券に口座を開設しておくべきべきです。なぜなら、特定口座やNISA口座が維持できると明記されているからです。
また、SBI証券が帰国された際に特定口座やNISA口座へ戻すことができるのなら、SBI証券も選択肢に入ってきます。
マネックス証券を利用されている方は楽天証券などへ株式を移動することを検討された方がよいでしょう。
下記記事でもご紹介しましたが、証券会社間の株式の移管手続きは非常に簡単です。

海外の証券口座や銀行口座を開設するのも一案
一方で、ネット証券3社に共通するのは「出国すると外国株を保有できない」点です。
そこで考えておきたいのが、海外の証券口座や銀行口座を開設して投資を継続する方法です。
高校中退投資家の場合はHSBC香港に銀行口座を保有しています。

海外の銀行や証券会社であれば非居住者であっても投資ができます。ただし、海外口座を管理するのは手間がかかるのも事実です。
そのため、「海外赴任中も投資を継続したい」という強い意思のある方や「将来海外で生活することがほぼ決まっている」ような方のみにしたほうがよいでしょう。
まとめ
本記事では海外転勤や海外移住時の証券会社の取り扱いについてご紹介しました。
海外転勤や海外移住時は日本の証券口座での取引は基本的に制限されます。株の取引はできませんが、楽天証券であればNISA口座や特定口座の継続も含めて可能です。
一方で、ネット証券大手3社では外国株式の保有はできません。外国株をどうしても保有し続けたいのなら海外の証券口座の開設も検討しなければいけません。
一定期間海外へ住むことが予想される方や検討されている方は、こういった情報も加味して証券会社を選定するとよいでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
海外転勤や海外セミリタイアする際の銀行口座の取り扱いについては下記記事でご紹介しています。




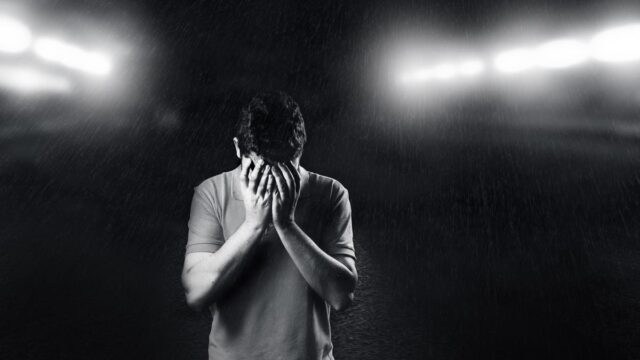






初めまして、直近で海外駐在の予定があるので、記事勉強になりました。
もし差支えなければお伺いしたいのですが、投資信託や株式をSBI証券→楽天証券に移管した場合、取得価格はどうなるのでしょうか。本記事を拝見して、メインで使っているSBIで保有しているファンドを楽天証券へ移管すること考えましたが、現在ある程度の含み益が出ているので、気になりました。
また、帰国して楽天証券の特定口座が復活した場合の取得価格についても併せてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます!
特定口座の場合、SBI証券から楽天証券に移管しても、SBI証券の取得単価がそのまま楽天証券に引き継がれます。
したがって、移管することで税金面で損することはありません。
また、海外から帰国された際も取得単価に変更はないとの理解で良いと思います。
海外駐在の間も特定口座は維持されますので、取得単価に変更が生じる要因はないと理解しています。
ただし、私はSBI証券→楽天証券へ移管した経験はありますが、海外駐在した経験はありません。帰国時の回答はあくまで参考程度にしていただければ幸いです。
dropoutinvestor さま
ご回答いただきありがとうございます。
こうした情報は貴重なので、大変参考になります。
帰国の際の状況については、
機会があったら楽天証券に確認してみます。
もう一つ、こちらは注意点といいますか、
ブログのネタにでもしていただければと思いますが、
楽天証券の場合、
①つみたてNISA,NISAは維持できるが、
②投資信託の分配金を「再投資する」に選択している場合、買い付けが発生するので保有できず、分配金コースを「受取型」へ変更する必要があるが、
③NISAで保有されている投資信託は、分配金コースの変更ができないため、課税口座へ振替後に分配金コースを「受取型」へ変更する必要がある、
という説明になっています。
私もそうですが、ほとんどの方、特に投資を始めた初心者は、楽天VTIなど、分配金が出ない投信についても分配金を「再投資する」ように選択していると思うのですが、そうすると、分配金のコースの変更ができないので、
せっかくコツコツ買い付けてきたNISAやつみたてnisaを、一度課税口座に移す必要があり、節税メリットがなくなってしまいます。
再度nisa口座に戻してもらえるとは考えにくいので、私は当月でつみたてnisaのつみたてをやめて、分配金を「受取」にできるよう、今までとは別の投信を買い付けていくことを考えています。分配金が出ない投信であれば当該選択をしてもあまり問題はないと思いますが、こうした点、今までつみたてをしてきた初心者が割を食うのはいかがなものか、と感じました。
あんじぇろ様
投資信託の取り扱いについて情報をありがとうございます。
確かにつみたてNISAを活用されている方にとっては不利な内容ですね。
実は数年前までは楽天証券は海外転勤時の口座維持は不可という回答でした。
各証券会社の対応は毎年のように更新されていますので、今後改善されていくことを期待したいと思います。
何か新しい情報が得られましたら、本ブログでもアップデートしていきたいと思います。